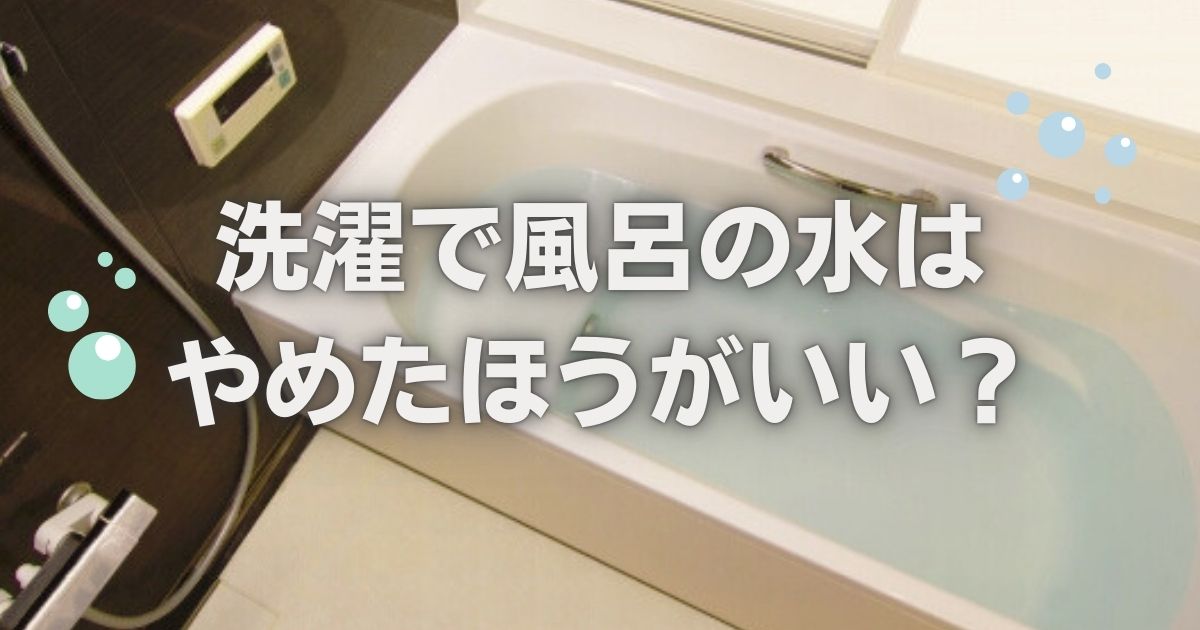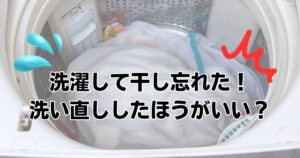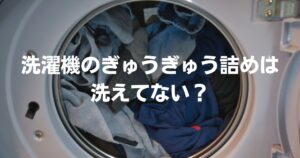風呂の残り湯を洗濯に再利用することは、多くの家庭で行われています。水道代を節約できると考える人も多いですが、実際のところ残り湯の洗濯はよくないのでしょうか。残り湯で洗濯するメリットとデメリットを知ることで、本当に続けるべきか判断しやすくなります。
残り湯を使えば水の使用量を抑えられるように思えますが、洗濯機への影響や衣類の衛生面など、気をつけるべき点も多くあります。特に、すすぎ1回と2回ではどのような違いがあるのか、また入浴剤を使用した風呂水での洗濯が問題ないのか、疑問を持つ人もいるでしょう。さらに、残り湯を衛生的に使うポイントを知ることで、トラブルを防ぐことができます。
また、残り湯で洗濯やめた場合の水道代がどの程度変わるのか、実際に洗濯に風呂水を使う人の割合はどれくらいなのかも気になるところです。
本記事では、これらの疑問を解決し、残り湯の洗濯が本当に節約になるのか、衛生面や洗濯機への影響を踏まえて詳しく解説します。
- 残り湯で洗濯するメリットとデメリット
- 衛生面や洗濯機への影響について
- 残り湯を使わない場合の水道代の変化
- 入浴剤やすすぎ回数が洗濯に与える影響
洗濯に風呂の水はやめたほうがいい?

- 残り湯で洗濯するメリット
- 残り湯で洗濯するデメリット
- 残り湯の洗濯はよくない?衛生面の問題
- 洗濯機への影響は?故障リスクを解説
- 風呂水洗濯、入浴剤使用時の注意点
残り湯で洗濯するメリット
お風呂の残り湯を洗濯に使うことには、いくつかのメリットがあります。
まず大きな利点として、水道代の節約が挙げられます。洗濯1回あたりに使用する水の量は、おおよそ50~60リットル程度ですが、このうち洗い工程に残り湯を使うことで、新たに水を使用する量を大幅に減らすことが可能です。
特に、毎日洗濯をする家庭では、長期的に見ると水道代の節約効果は無視できないほど大きなものになります。
さらに、残り湯は水温が比較的高いため、洗浄力の向上にもつながります。冷たい水よりも温かいお湯のほうが汚れを落としやすく、特に皮脂汚れや油分を含んだ汚れが多い衣類には効果的です。
そのため、冬場の寒い時期などは、冷水での洗濯よりも残り湯を使うことで、洗剤の効果を高めることが期待できます。
また、環境負荷の軽減もメリットのひとつです。洗濯で使う水の量を減らすことは、水資源の節約につながり、環境保護の観点からも有効な取り組みといえます。
特に、節水意識の高い人にとっては、毎日の生活の中でできる小さなエコ活動のひとつとして、残り湯の活用はおすすめです。
このように、水道代の節約・洗浄力の向上・環境負荷の軽減という3つの点から、残り湯を洗濯に利用することにはメリットがあるといえるでしょう。
残り湯で洗濯するデメリット

一方で、残り湯を洗濯に使用することには、デメリットもあります。
まず第一に、衛生面の問題が挙げられます。お風呂の残り湯には、皮脂や汗、石けんカスなどが含まれており、目には見えなくても雑菌が繁殖している可能性があります。特に気温の高い季節は、時間が経つほど細菌が増えやすく、においやカビの原因になることもあります。
後述しますが、洗濯機への影響も無視できません。残り湯に含まれる汚れや細菌が洗濯槽に付着し、カビやぬめりの発生を促進する可能性があります。
定期的に洗濯槽の掃除をしないと、洗濯機自体の衛生環境が悪化し、最終的には洗濯物に悪影響を及ぼすことにもつながります。
こちらも後述しますが、入浴剤を使用した場合は注意が必要です。特に香りや成分が強い入浴剤を入れた残り湯を洗濯に使うと、衣類に成分が残ってしまったり、洗濯機に悪影響を与えることがあります。
特定の成分が衣類の繊維にダメージを与える可能性もあるため、使用する入浴剤の種類によっては、残り湯を洗濯に使わないほうがよい場合もあります。
このように、残り湯を洗濯に使うことには、水道代の節約や洗浄力向上といったメリットがある一方で、衛生面や洗濯機への影響、入浴剤の問題といったデメリットも考慮する必要があります。
残り湯の洗濯はよくない?衛生面の問題

残り湯での洗濯に関して「よくないのでは?」と心配する人が多い理由のひとつに、衛生面の問題があります。
お風呂の残り湯には、人の皮脂や汗、さらには目に見えない微生物が含まれており、時間が経つほど雑菌が増殖しやすくなります。特に気温が高い季節や、長時間放置された残り湯は、細菌が繁殖するリスクが高まるため、衛生的に問題が生じやすくなります。
また、残り湯を使うことで洗濯物に雑菌が付着し、生乾きの嫌な臭いの原因になることもあります。
通常の洗濯ではある程度の菌は除去されますが、湿度の高い環境や乾燥が不十分な場合、菌が増殖してしまうことがあります。
そのため、特にタオルや下着などの直接肌に触れる衣類を洗う際には、残り湯の使用を避けるのが無難です。
この問題を解決するためには、残り湯を衛生的に使う工夫が必要です。例えば、残り湯を使うのは「洗い工程のみにする」「すすぎは必ず清潔な水で行う」などの対策を取ることで、雑菌の影響を最小限に抑えることができます。
洗濯後の洗濯機をしっかり乾燥させることや、定期的に洗濯槽クリーナーを使うことも重要です。
衛生面の問題を考えると、残り湯の使用には慎重になるべきですが、適切な使い方をすればリスクを減らすことは可能です。
日常的に残り湯を使う場合は、こうした工夫を取り入れて、清潔さを保つよう心掛けることが大切です。
洗濯機への影響は?故障リスクを解説
お風呂の残り湯を洗濯に使うことは節水や洗浄力の向上といったメリットがありますが、洗濯機への影響も考慮する必要があります。特に、洗濯機の故障リスクが高まる要因には注意が必要です。
まず、残り湯には皮脂や石けんカス、髪の毛などの汚れが含まれています。これらが洗濯機のフィルターやホースに蓄積すると、詰まりの原因になることがあります。
特に、長期間にわたって残り湯を使い続けると、洗濯機内部に汚れがたまりやすくなり、排水の流れが悪くなる可能性があります。これが悪化すると、最終的には排水不良や洗濯機の動作不良を引き起こす原因となることもあるため、定期的な掃除が欠かせません。
また、残り湯に含まれる雑菌やカビの影響も無視できません。洗濯槽の裏側やホース内に湿気がこもると、カビが繁殖しやすくなります。
その結果、洗濯物に嫌な臭いがついたり、洗濯機の内部が劣化しやすくなったりする可能性があります。特にドラム式洗濯機の場合は、湿気がこもりやすいため、定期的な洗濯槽クリーニングが必要です。
さらに、残り湯を汲み上げるポンプの故障リスクも考慮すべきポイントです。
多くの洗濯機には風呂水をくみ上げるための専用ポンプが付属していますが、使用頻度が高くなるとフィルターに汚れがたまりやすくなり、吸水力が低下することがあります。
最悪の場合、ポンプが目詰まりを起こし、使えなくなってしまうこともあるため、こまめにフィルターを掃除することが重要です。
洗濯機の寿命を延ばすためには、残り湯の使用後に洗濯槽をしっかり乾燥させることや、月に一度は洗濯槽クリーナーを使うことが推奨されます。
洗濯機の取扱説明書を確認し、メーカーが推奨する使用方法を守ることも大切です。残り湯の利用は便利ですが、洗濯機への負担を最小限に抑える工夫をしながら活用するようにしましょう。
風呂水の洗濯、入浴剤使用時の注意点

入浴剤を使用した残り湯を洗濯に使うことは可能ですが、いくつかの注意点があります。入浴剤の成分によっては、衣類や洗濯機に悪影響を及ぼすことがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
まず、入浴剤には香料や着色料が含まれていることが多く、これらが衣類に残ってしまうことがあります。
特に白い衣類や薄い色の服に色移りする可能性があるため、注意が必要です。色付きの入浴剤を使った残り湯は、できるだけ洗濯には使わないほうが安全です。
また、保湿成分やオイルが含まれている入浴剤にも注意が必要です。これらの成分は衣類の繊維に付着しやすく、洗浄力を低下させる原因になることがあります。
特に吸水性が求められるタオル類に使うと、ふんわり感が損なわれたり、水分をうまく吸収できなくなったりすることがあるため、避けたほうがよいでしょう。
さらに、洗濯機への影響も考慮すべき点です。入浴剤の成分が洗濯機の内部に残ることで、ぬめりやカビの発生を促進する可能性があります。特に、粘度の高い入浴剤を使った場合、洗濯槽や排水ホースの汚れが蓄積しやすくなるため、定期的に洗濯機を掃除することが重要です。
入浴剤を使った残り湯を洗濯に活用したい場合は、使用する入浴剤の成分を事前に確認し、「洗濯に適したもの」を選ぶことが大切です。
無色透明で保湿成分の少ないものを選ぶことで、衣類や洗濯機への悪影響を最小限に抑えることができます。
メーカーによっては、洗濯にも使える入浴剤を販売している場合もあるため、こうした商品を選ぶのもひとつの方法です。
このように、入浴剤の種類によっては、洗濯に適さないものもあるため、慎重に選ぶ必要があります。できるだけ洗濯への影響を避けるためには、入浴剤を使わない日を設け、その日の残り湯だけを洗濯に利用するなどの工夫をするとよいでしょう。
洗濯に風呂の水はやめたほうがいい?やめた場合の影響は?
- 残り湯の洗濯は節約にならない?
- 残り湯で洗濯をやめた場合の水道代は?
- 残り湯を衛生的に使うポイントとは?
- 風呂水洗濯はすすぎ1回or2回、どっちが正解?
- 洗濯に風呂水を使う人の割合を調査
残り湯の洗濯は節約にならない?

お風呂の残り湯を洗濯に使うことは節水にはなるものの、トータルバランスで見ると必ずしも節約につながるとは言えません。
水道代の削減を目的に残り湯を活用する人も多いですが、その他のコストや手間を考慮すると、期待したほどの節約効果が得られないこともあります。
まず、残り湯を洗濯に使う場合、給水ホースやポンプを使用することが一般的です。
これらの機器を使用することで電気代が発生します。特に、風呂水ポンプを頻繁に使用する場合、電力消費が増え、結果的に節約効果が薄れることもあるのです。
また、残り湯には皮脂や石けんカスが含まれており、そのまま使用すると洗濯物の汚れが落ちにくくなる可能性があります。
そのため、通常より多めの洗剤や酸素系漂白剤を使うことになり、洗剤代がかさんでしまうことも考えられます。さらに、すすぎの際にはキレイな水道水を使う必要があるため、節水効果も限定的です。
もう一つ見落としがちなのが、洗濯機のメンテナンス費用です。残り湯を長期間使用すると、洗濯槽やホースの内部に汚れが溜まりやすくなり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
そのため、洗濯槽クリーナーを使う頻度を増やしたり、洗濯機の定期的なメンテナンスが必要になったりするため、結果的に維持費が高くつくことがあります。
このように、残り湯の活用には節水のメリットがある一方で、電気代・洗剤代・メンテナンス費用といったコストも発生します。これらを総合的に考えると、必ずしも大幅な節約になるとは言い切れません。
もし節約を重視するなら、洗濯機の使用回数を減らす、エコモードを活用するなど、別の方法も検討するのがよいでしょう。
残り湯で洗濯をやめた場合の水道代は?

残り湯を使った洗濯をやめると、水道代がどの程度変化するのか気になるところです。実際には、家庭の洗濯頻度や洗濯機の種類によって違いはありますが、そこまで大きな負担増にはならない場合が多いです。
一般的に、洗濯1回あたりに使用する水の量は、縦型洗濯機で約100L、ドラム式洗濯機で約50L程度です。(※洗濯機の種類によって異なります)これを水道料金に換算すると、1回あたり約20〜40円程度の水道代がかかる計算になります。
<縦型洗濯機の定格洗濯時の水道代>
1Lあたりの水道単価0.24円で算出(東京都水道局)
この数値で計算すると、100×0.24=24円となります。
例えば、毎日『洗い』の工程で約60Lの残り湯を利用していたとして、残り湯洗濯をやめた場合、1ヵ月で約430円、年間で5160円の増額になります。(60L×30日。1Lあたりの水道代を0.24円として、増額分を1800L×0.24円/Lで算出)
しかし、これは地域の水道料金単価や、使用する洗濯機の節水性能によっても変動するため、正確な金額を知りたい場合は、お住まいの自治体の水道料金を確認することをおすすめします。
また、最近の洗濯機は節水性能が向上しており、昔に比べると水道代の負担は軽減されています。特にドラム式洗濯機は、もともと使用する水量が少ないため、残り湯を使用しなくても水道代の増加を抑えることができます。
さらに、水道代が増える代わりに、残り湯を使わなくなることで、洗濯槽の汚れが溜まりにくくなり、メンテナンスの手間や洗剤・漂白剤の使用量を減らせるというメリットもあります。
加えて、残り湯をくみ上げるポンプを使わないことで、電気代の節約にもつながります。
つまり、残り湯を使った洗濯をやめた場合の水道代は、月数百円程度の増加にとどまるケースが多いですが、その分、洗濯機のメンテナンス費用や電気代が下がる可能性もあります。
総合的に見れば、必ずしも水道代の増加が大きな負担になるわけではないため、メリットとデメリットを比較しながら判断するとよいでしょう。
残り湯を衛生的に使うポイントとは?

残り湯を洗濯に利用する際、衛生面が気になる方も多いでしょう。
残り湯には皮脂や汗、石けんカスなどの汚れが含まれており、適切に管理しないと雑菌が繁殖し、衣類や洗濯機に悪影響を与えることがあります。ここでは、残り湯を衛生的に使うためのポイントを紹介します。
まず、もっとも重要なのは「残り湯の使用タイミング」です。入浴後の残り湯は時間が経つほど雑菌が増えやすくなります。特に、気温が高い夏場は雑菌が繁殖しやすいため、できるだけ入浴後すぐに使うのが理想的です。もし翌日に使う場合は、浴槽にフタをする、または風呂水用の除菌剤を入れると、雑菌の繁殖を抑えることができます。
「残り湯の使い方」にも注意が必要です。基本的に、洗濯の「洗い」工程でのみ使用し、「すすぎ」は水道水を使うのが衛生的です。残り湯ですすぐと、洗濯物に汚れや雑菌が付着したまま乾燥することになり、嫌なニオイの原因になることもあります。特に肌着やタオル類は、すすぎに清潔な水を使うことで、より衛生的に仕上げることができます。
また、「定期的な洗濯機の掃除」も欠かせません。残り湯を使い続けると、洗濯機の内部に雑菌がたまりやすくなります。洗濯槽クリーナーを月に1回程度使用することで、カビや汚れを防ぎ、清潔な状態を保つことができます。特にドラム式洗濯機は湿気がこもりやすいため、使用後は扉を開けて換気することも大切です。
さらに、「衣類の種類を選ぶ」のもポイントの一つです。肌に直接触れる衣類やタオル類は、できるだけ清潔な水で洗いたいものです。残り湯を使用するのは外出着や厚手の衣類に限定し、デリケートな衣類には使わないようにするのもよい方法です。
このように、いくつかの工夫をすることで、残り湯を衛生的に使うことが可能です。適切な管理をしながら、洗濯の節水と清潔さを両立させるよう心がけましょう。
風呂水洗濯はすすぎ1回or2回、どっちが正解?

洗濯に風呂水を使用する場合、「すすぎは1回でいいのか、それとも2回必要なのか?」と迷う人も多いでしょう。結論としては、衣類の汚れ具合や衛生面を考慮すると、基本的にはすすぎは2回がおすすめです。ただし、状況によっては1回でも問題ない場合もあります。
まず、すすぎ1回で済ませる場合のメリットは「節水と時短」です。
最近の洗剤にはすすぎ1回でOKとされているものも多く、そうした洗剤を活用すれば水の使用量を抑えながら、洗濯時間を短縮することができます。ただし、風呂水を使った洗濯では、すすぎ1回だけだと皮脂汚れや雑菌が十分に落ち切らず、衣類に臭いが残る可能性があります。特に、タオルや肌着など、直接肌に触れる衣類は慎重に扱う必要があります。
一方で、すすぎを2回行うと、洗剤の残留や汚れの再付着を防ぐことができます。
風呂水を使用すると、湯に含まれる皮脂やせっけんカスが衣類に残りやすくなりますが、すすぎを2回行えばそれらをしっかり洗い流すことができます。また、柔軟剤を使用する場合も、1回目のすすぎで洗剤を落とし、2回目のすすぎで柔軟剤を均一に浸透させることができるため、ふんわりとした仕上がりになります。
また、風呂水を使う場合、すすぎの工程では水道水を使うのが基本です。
洗いの工程に風呂水を使うのは問題ありませんが、すすぎまで風呂水を使ってしまうと、雑菌が残るリスクが高まります。
特に、気温が高い夏場は雑菌が繁殖しやすく、部屋干しすると生乾き臭の原因になることもあるため、すすぎは必ず清潔な水道水を使用するのがベストです。
結局のところ、風呂水を使う洗濯ではすすぎは2回が望ましいですが、すすぎ1回用の洗剤を活用する場合や、汚れが少ない衣類を洗う場合は、1回でも問題ないことがあります。家庭の状況や衣類の種類によって、最適なすすぎ回数を選ぶようにしましょう。
洗濯に風呂水を使う人の割合を調査

風呂水を洗濯に使用する家庭はどのくらいあるのでしょうか。実際のデータをもとに調査すると、風呂水を活用する人の割合は一定数存在しているものの、すべての家庭が利用しているわけではありません。
調査方法によって異なりますが、ある調査によると約30〜40%の家庭が風呂水を洗濯に利用しているというデータがあります。特に、節水意識の高い家庭や、使用水量が多くなる大家族では、風呂水を活用する傾向が強いようです。
一方で、共働き世帯や単身世帯では、風呂水を利用する手間を考慮して、水道水のみで洗濯するケースが多いと言われています。
また、地域ごとの違いもあります。例えば、水道料金が高い地域では、少しでも節約するために風呂水を使う割合が高くなる傾向があります。
反対に、水道代が比較的安い地域では、風呂水を使うメリットが少なく、利用率は低めになることが多いようです。
さらに、洗濯機の種類によっても、風呂水を使用するかどうかが変わってきます。
縦型洗濯機を使用している家庭では風呂水を使う割合が高いのに対し、ドラム式洗濯機を使用している家庭では風呂水を利用するケースは少なめです。
これは、ドラム式洗濯機がもともと使用する水量が少なく、風呂水を使うメリットがあまりないためです。また、ドラム式洗濯機の一部には、風呂水ポンプが取り付けにくい機種もあり、それも利用率の低さにつながっています。
なお、最近では「風呂水を使うことによる衛生面の懸念」を理由に、風呂水を洗濯に利用しない家庭も増えてきています。
特に、梅雨や夏場は雑菌が繁殖しやすく、洗濯物の臭いの原因になることがあるため、水道水を使用する方が安心だと考える人も多いようです。
その一方で、風呂水用の除菌剤を活用したり、適切なメンテナンスを行いながら風呂水を使う家庭もあり、利用方法は多様化しています。
お風呂の残り湯を洗濯に使っていますか? ウェザーニュースが2019年に行った調査によると、「使っている」が3,376人(34%)、「使っていない」が6,694人(66%)という集計結果になりました。(回答数9692人)
引用元:ウェザーニュース(2019/07/22)
ウェザーニュースで「お風呂の残り湯を洗濯に使う?」というアンケート調査を実施したところ、「よく使用する」が19.6%、「たまに使用する」が9.8%だったのに対し、「使用しない」は70.6%に上りました。
引用元:ウェザーニュース(2024/09/15)
洗濯に風呂の水はやめたほうがいい:総括
記事のポイントをまとめます。
- 再利用した風呂の水には雑菌が多く含まれ、衛生的に問題があるため避けるべきである
- 皮膚トラブルの原因となる細菌やカビが繁殖しやすく、アレルギーや肌荒れを引き起こす可能性がある
- 風呂の残り湯を使用すると、洗濯物に独特の嫌な臭いが残りやすく、清潔感が損なわれる
- すすぎに再利用水を使うと洗剤が十分に落ちず、衣類に汚れや洗剤カスが残ることがある
- 風呂の水を使い続けると、洗濯機の内部に雑菌が繁殖し、故障や異臭の原因となる可能性がある
- カビやぬめりが発生しやすくなり、洗濯槽の掃除を頻繁に行わないと衛生状態が悪化する
- 再利用水に含まれる皮脂や汚れが洗剤の成分と反応し、洗浄力が低下してしまうことがある
- 風呂の水を使った洗濯では、白い衣類が黄ばみやすく、色柄物がくすんでしまうことがある
- 目に見えない雑菌が洗濯物に付着する可能性があり、着用時に健康リスクを高める恐れがある
- 再利用水に含まれる汚れや雑菌が原因で、衣類の繊維が傷みやすくなり、寿命を縮めることがある
- 風呂水の独特な臭いが洗濯物に移ると、乾燥後も不快な臭いが残り、着用時に気になることがある
- 排水ホースや洗濯槽の内部に汚れが蓄積し、定期的な掃除を怠るとカビや悪臭の原因となる
- 風呂水は水道水に比べて衛生面で劣るため、赤ちゃんや肌の弱い人がいる家庭では特に注意が必要である
- 衣類やタオルを洗濯した際に、残り湯に含まれる雑菌が広がり、家庭内の感染症リスクを高める可能性がある
- 風呂の水を長期間洗濯に再利用し続けると、蓄積された汚れや細菌が影響し、健康被害につながる恐れがある